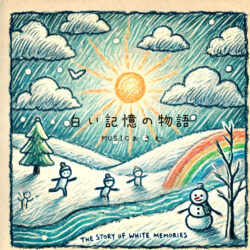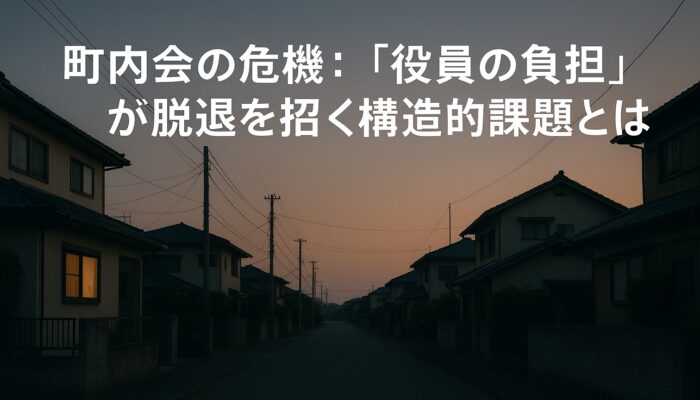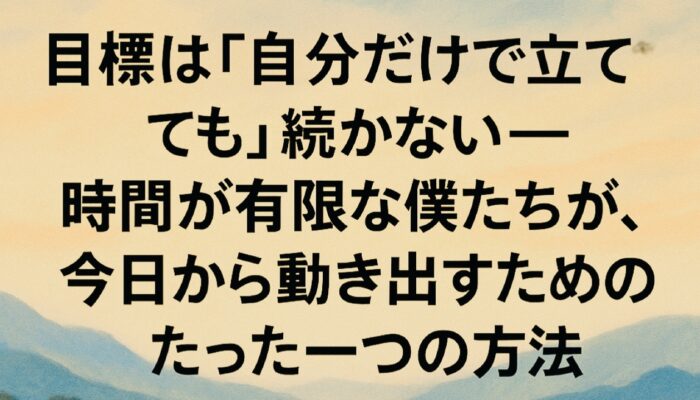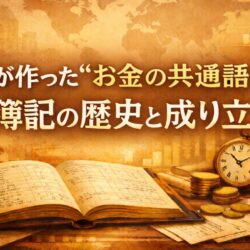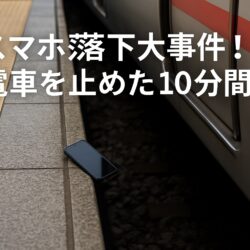おはよう。今日もいい天気。今日は週末の土曜日。とはいえ、明日は午前中は自治会の役員会があり、午後からはキャリアコンサルティング技能士の二次試験本番。まる一日が忙しさに包まれる予定なので、今日は心と身体を整えて過ごしたい。生活を、丁寧に楽しみたい。
明日の自治会では、今多くの地域で共通する課題、「脱退の増加」にどう向き合うかが話題になる。これは自治会に限った話ではなく、PTAや職場の組合など、かつては“参加して当然”だった任意団体で同様の現象が起きている。背景には、「活動の負担」「役割の重さ」「関心の薄れ」「成果の見えづらさ」など、構造的な問題が共通して潜んでいる。
広島市をはじめ、全国の自治体が実施した調査を見ていても、都市部を中心に自治会の加入率は年々低下し、特に若年世帯や子育て世帯では顕著だ。参加しない理由は、「やることが多くて大変」「役員になるのが不安」「会費の使い道が不透明」「行事に興味が持てない」などが並ぶ。これはそのまま、PTAや職場の組合でも繰り返し語られてきた理由でもある。
特に近年では、子ども会の解散や地域の祭りの縮小など、地域コミュニティの象徴的な活動が消えていくことで、「関わりたくても関われない」「関わっても意味が感じられない」と感じる人が増えているように思う。中には、役員報酬を設けて担い手を確保しようとした自治会もあるが、必ずしも参加者の増加や活動の活性化にはつながっていない。報酬が導入されることで「損得の構図」が生まれ、かえって信頼や協力が損なわれてしまう事例もあった。
お金を出せば人が集まるという発想は、地域活動にはなじみにくい。むしろ必要なのは、「自分のペースで無理なく関われる空気」と「参加への納得感」だ。実際、多くの人は地域を嫌っているわけではない。「災害時には近所の人がいて安心だった」「ごみ出しルールを教えてもらえて助かった」「子どものイベントで地域のありがたみを感じた」──そんな温かいエピソードを抱えている人も少なくない。
だからこそ、「強制ではなく、選べる仕組み」を作っていくことが大切だと感じている。今回、僕たちの自治会では初めて本格的なアンケートを実施する予定だ。どんな活動に興味があるか、何が負担に感じるのか、役員についてどんな不安を抱えているか、そして、自治会という存在そのものをどう捉えているか──そういった声を、押しつけがましくなく、でも丁寧に聴きとりたい。
興味のない人には、さっと済ませられるように。関心のある人には、しっかり書けるように。そんな設計にこだわった。自治会の未来は、きっと「全員が積極的に参加すること」ではなく、「一人ひとりが気持ちよく関われる範囲を選べること」にかかっている。今ある仕組みに誰もが合わせるのではなく、これからの時代に合った仕組みに、こちらが合わせていくこと。その柔軟さが、地域を救う鍵になる。
そしてこれは、自治会だけでなく、PTAも組合も、地域社会のあらゆる“古くて新しい”仕組みに通じるテーマだ。関わり方に余白があるからこそ、人はそこに「自分の役割」を見出せるのだと思う。
今日を丁寧に生きることが、明日をやさしくつなぐことにつながる。明日は試験。自分自身の節目でもある。遠くにいる家族も、近くにいる家族も、それぞれの場所で、それぞれのペースで、一生懸命に今日を生きている。そのことが、ただただ誇らしく、愛おしい。
さぁ今日は、のんびり生活を楽しもう。
同じ空の下、心はいつも隣にある。今日も、心から愛している。
今日もありがとう。またね。
- ✍️人が作った“お金の共通語”|簿記の歴史と成り立ち
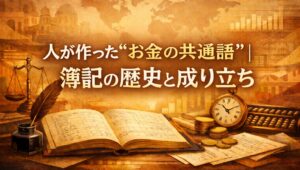
- ✍️通学路の危険は放置しない|信号も横断歩道もない交差点、「誰に言えばいい?」を解決する:見守り隊・警察・道路管理者・学校の役割分担と正しい動かし方

- 町内会・自治会の役員が決まらない問題を終わらせる|退会・揉め事を減らす「決め方」7選と会議テンプレ

- ✍️ロブロックス – Robloxって何が面白いの?子どもがハマる理由と「遊ぶ・作る・稼ぐ」世界の正体

- ✍️家事育児が「私だけ重い」から抜け出す──現代夫婦の分担設計図

- ✍️安倍元首相銃撃事件:山上徹也被告に無期懲役判決|事実の整理と、情報に飲まれないための構え

- ✍️これから伸びる社会課題解決ビジネスの共通点──現場が燃え尽きない仕組みの設計

- ✍️2026年に静かに近づく10のリスク|政治・経済・テクノロジー・仕事とキャリアの下降トレンド地図

- ✍️2026年のビッグチャンスを掴む10のキーワード|政治・経済・テクノロジー・仕事とキャリアのトレンド地図

- ✍️温暖化の時代に「なぜ大雪が降るのか」──気候変動の現在地と、世界と日本で起きていること

- ✍️クリスマスの由来、結局なにが本当?──12月25日・西暦・日本の歴史雑学と真実
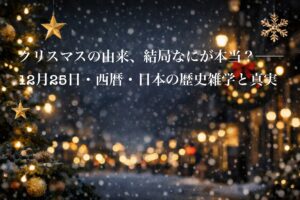
- ✍️ふるさと納税、結局得なの?損なの?──現金・投資・返礼品を全部「同じ土俵」で徹底比較検証
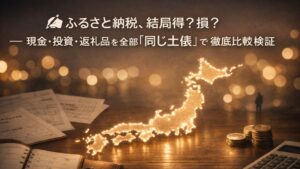
- ✍️なぜ迷惑メールは消えないのか──詐欺が“成立してしまうビジネスモデル”の裏側

- ✍️オーストラリアが未成年のSNSを禁止した理由──スマホ時代に「子どもを守る」とは何か
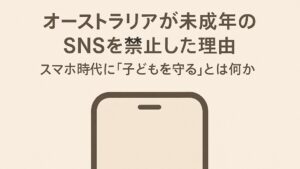
- ✍️育児の負担は、どうしていつも女性に寄るのか──制度が整っても解消しない“静かな不平等”と、必要な社会の設計

- ✍️米国が台湾側に舵を切った日──「台湾保証法」が東アジアの勢力図を塗り替える理由
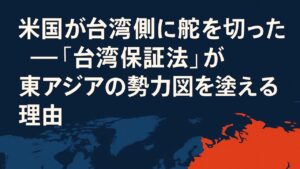
- ✍️性の多様性をすべて整理する──LGBTQ+の言葉・歴史・社会背景と、ノンバイナリー/Xジェンダーの位置づけを分かりやすく解説する

- ✍️歳を重ねたとき、持ち家をどうするか──親世代が家を守る立場と、子ども世代が実家について考えるべきこと

- ✍️台湾有事をめぐる“大誤解”──日本が今まさに直面している危険な現実

- ✍️クマが悪いんじゃない──変わったのは、地球と僕たちのほうだ。でも…

- ✍️あなたの意見は“本当に自分の意見”か──グループダイナミックスが操る無意識の力
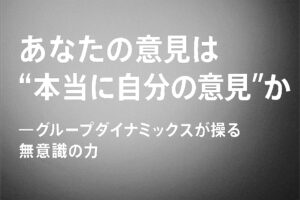
- ✍️日本初の女性総理大臣誕生 何が変わり、何が問われるのか

- ✍️なぜ自治会から若者が離れていくのか──“祭りの席”が映す、世代交代できない日本社会のリアル

- ✍️防衛強化と国家予算──「軍拡」か「自立」か、日本が戦後80年ぶりに問われる“覚悟”

- ✍️日本初の女性総理・高市早苗の登場──保守と変革のあいだで、日本はどこへ向かうのか
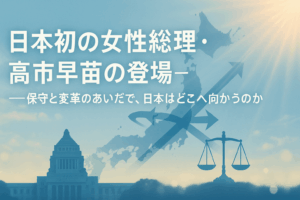
- ✍️パワハラ防止法では救えないグレーゾーン──ガスライティングとゲーム理論に学ぶ気づきと対処法
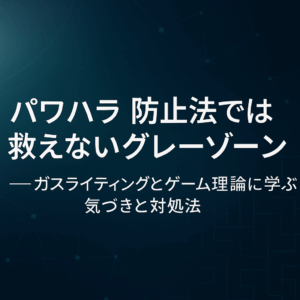
- ✍️働く母も父も本当に救われるのか──令和7年10月改正育児・介護休業法、その理想と現実の溝
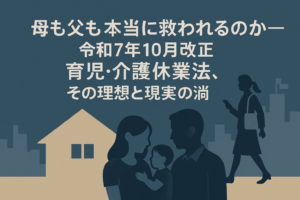
- ✍️実質賃金はマイナス、最低賃金は過去最高──なぜ日本人は豊かさを実感できないのか

- ✍️国民は選べない総裁選──それでも僕らが考えておきたいこと
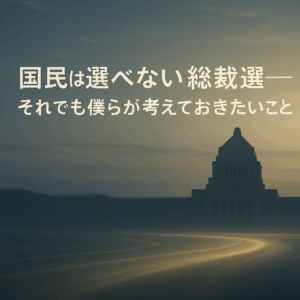
- ✍️秋分の日──自然と人を結ぶ季節の節目