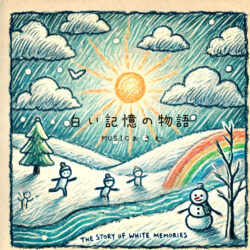おはよう。今日の空は、まるで薄い雲のベールをかけたように淡く、そこに太陽の光がゆっくり染みわたっている。眩しさはないのに、光はちゃんと感じられる。こんな朝は、優しい気持ちなれる。
さて、「音楽は感性のもの」とよく言われるけれど、実はその奥には、美しく組まれた“数の仕組み”がある。ピタゴラスが見抜いた音の数学。ポップスに響く感情のコード。
そんな魔法のような構造美を、今日、僕の言葉で紐解いてみたい。昨日に続いて、今日もまた、音楽の話をするよ。今日は「音楽理論」、とくにコードの構造について。僕が何年もかけて夢中になった、人生の一部のような世界について。
僕が音楽理論に本気でのめり込んだのは、ギターを自由に操りたかったから。ただそれだけの理由だった。でもその「自由に」という言葉の奥には、すごく強い渇きがあった。指板の上を感覚じゃなく、意図して動けるようになりたかった。耳で覚えたコードではなく、理屈で理解した音を、思い通りに鳴らせるようになりたかった。
その思いで始めた学びが、気づけばA4で500ページ近い、自分だけの理論ノートになっていた。内容は基礎から、かなりマニアックな世界まで。今見返しても、「よくここまでやったな」と思う。けど、当時の僕にとっては、それが普通だった。
もちろん全部を完璧に覚えているわけじゃない。今だって、ギターが自由に弾けるようになったわけではない笑。けれど、一度でも「本気で理解しようとした時間」があるという事実は、今も僕の支えになっている。たとえば、なんとなく押さえていたコードフォームが、「ああ、この音はこういう仕組みだったんだ」とつながる瞬間。耳と指と頭が、スッと同じところに落ち着くような感覚。それが、音楽理論と出会った僕が、何度も味わった小さな感動だった。
音楽理論というと、堅苦しく聞こえるかもしれない。でも実は、とても人間的な学問だと思う。感情と構造が、美しく絡み合っている。そしてそれは、古代の昔からずっと、変わっていない美しさでもある。
紀元前のギリシャ。数学者ピタゴラスは、音楽を「数」で説明できることを発見した。弦の長さを変えて音を鳴らす実験の中で、たとえば1:2(オクターブ)、2:3(完全五度)、3:4(完全四度)など、耳に心地よく響く音の組み合わせには、音の高さ(周波数)の間に“美しい整数比”があることに気づいた。つまり、音楽とは周波数の比──数の関係で成り立っているという考え方が、音楽理論の最初の礎だった。それから二千年以上経った今でも、僕たちはその思想の延長線上に立っている。
たとえば、Cメジャーキー。ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シという七つの音から、C、Dm、Em、F、G、Am、Bdimというコードが生まれる。この七つのコードは、それぞれ「Ⅰ(トニック)」「Ⅱm(サブドミナントマイナー)」「Ⅲm」「Ⅳ(サブドミナント)」「Ⅴ(ドミナント)」「Ⅵm」「Ⅶdim」という“度数”の概念で整理される。たとえば、「C→G→Am→F」という進行は、「Ⅰ→Ⅴ→Ⅵm→Ⅳ」という構造を持っている。
この“度数”という考え方を使えば、どんなキーでも同じ構造で進行を読み解ける。Cがトニックなら、Gはドミナント。でも、GがトニックになればDがドミナント。キーが変わっても“役割の流れ”は変わらない。コード進行を感覚ではなく構造で理解すること。それが、理論の大きな強みだと思う。
コード進行って、まるで映画のシーン構成みたいなんだ。明るく始まって、揺れて、切なくなって、また戻ってくる。ただの和音が、物語を持ちはじめる。
理論を知っていると、「なぜ気持ちよく聞こえるのか」がわかる。そして、「なぜ、あの曲があんなに切なかったのか」も、わかるようになる。Fコードの中の“ラ”が、Gコードで“ソ”に落ちる。その1音の変化が、自然で、美しい。
コードそのものの構造も、知れば知るほど奥が深い。Cというコードは「ド・ミ・ソ」でできている。“ド”がルート、“ミ”が長3度、“ソ”が完全5度。この3つが積み重なることで、Cメジャーという響きができる。マイナーコードは3度の音が半音下がって“ミ♭”になる。それだけで、響きの印象は一変する。積む音が変われば、性格が変わる。それがコードの面白さだ。
そこにテンションと呼ばれる“飾りの音”を加えると、さらに世界が広がる。「Cmaj7」は“ド・ミ・ソ・シ”。“シ”という7度の音が入るだけで、透明感と余韻が生まれる。「C9」では“レ”が加わって、ちょっとジャジーな響きになる。同じコードでも、積まれる音が変わるだけで、まるで別人のような表情になる。
それに、五度圏。コードの関係を円で捉えると、どのコードも隣り合う関係が自然につながっている。CからGへ、GからDへ。時計回りに進むだけで、耳が安心する進行になる。だから、どこへ進んでも、最後にはまた“戻ってこられる”。音楽理論の中でも、この“循環する感覚”は特に好きなところだ。
もちろん、理論がすべてじゃない。感覚だけでできた曲も、偶然に生まれたメロディも、どれも正解だと思う。でも、理論を知ると、偶然じゃなくて“選んだ音”になる。理由があって選んだ音は、自分の中にしっかりと響く。その響きは、たとえ聴き手に説明できなくても、不思議と伝わる。
今も、自分のノートをときどき見返すたびに思う。「こんなに夢中になってたんだな」って、少し泣きそうになる。将来、もし子どもたちが音楽に夢中になったら、このノートを見せてあげたい。でも、「これで勉強しなさい」なんて言いたくない。ただ、「こんなふうに夢中になっていいんだよ」という姿を、そっと置いておきたい。
学ぶって、面白い。知るって、豊かだ。どんなに学んでも、すべてはいつか忘れていく。それでも、人は学びたくなる。限られた時間の中で、何かを深く知りたくなる。それは、生きている証拠かもしれない。
今週末は、キャリアコンサルティング技能士の二次試験。昨日も仲間たちと夜遅くまで模擬練習をした。心を使って、耳を傾けて、自分の中にある「ほんとうのこと」を取り出す。今日も忙しい一日になりそうだ。でも、それもまた幸せなこと。ひとつひとつの経験が、自分のコード進行の中で、ちゃんと役割を果たしている気がする。
そして、今日も、愛する家族の名前をひとりずつ思い浮かべて、心の中で「ありがとう」と言う。みんながそれぞれの人生を、今日も懸命に生きている。信じてる。誇りに思ってる。愛してる。
今日もありがとう。
バイバイ。