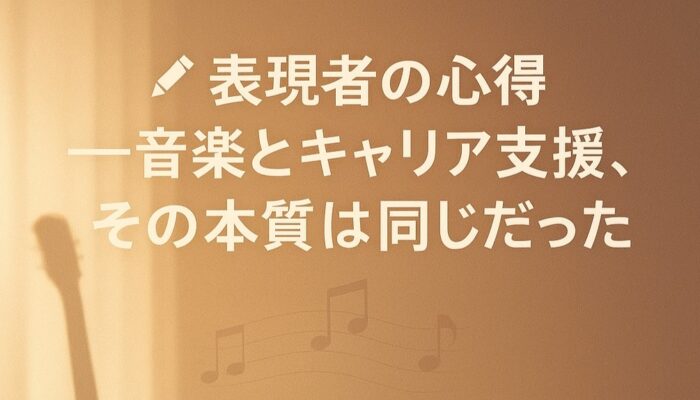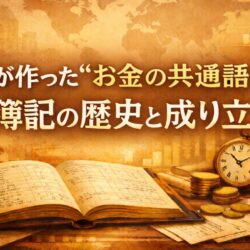おはよう。今朝は少し曇っていて、小雨が降っている。でも、不思議と暗さはなく、むしろ明るく感じる。まるで春を歓迎しているような雨だ。鳥たちの鳴き声もどこか弾んでいて、川の流れも軽やかに見える。こういう景色の見え方は、きっと自分の心の状態を映しているんだろう。少しざわつく感じはあるけれど、それもまた季節の変化とともに動いている証拠だと思う。
昨日もボイストレーニングに取り組んだ。普段から考察している発声の仕方について、改めて整理し、実践を繰り返した。自分の今の状態を客観的に確認し、必要な調整を加えていく。できている部分はしっかり認識し、まだ不十分な部分は修正する。新しい情報を加えながら、これまでの知識や分析を統合し、より安定した発声ができるようにしていく。
前回よりも確実に良くなっている。声の響きが軽くなり、力みが減ったことで、無駄な抵抗がなくなっているのがわかる。でも、まだもっと楽に出せる。力を抜いて余裕を持たせれば、もっと自然に響くはずだ。今はまだ少し無意識の緊張が残っている感じがある。それを取り除けば、もっとシンプルに、無駄のない声になる。
ミックスボイスを安定させるには、口の中や鼻の奥の響きを適切にコントロールすることが鍵になる。特に、口腔の響きを基礎に、鼻腔共鳴をしっかり活かすことが重要だ。鼻から息漏れする声でも鼻声でもないけれど、限りなく鼻声に近いイメージで、頭の中や顔の前が響いてうるさいような感覚を探り、その形に持っていく感じだ。そのために、軟口蓋の位置を適切に保ち、表情筋を使って鼻腔の広さや形を変えながら、ピッチに合わせて共鳴ポイントを維持・微調整することが求められる。
さらに、喉の奥(咽頭腔)を開いて深い響きを作ること、胸の共鳴を活かすこと、舌の奥を下げる意識を持つことも必要になる。鼻に響きを集めつつ、口からしっかり息を圧出し、漏れのない速い息の通り道を確保することで、よりスムーズに声が流れる。地声に戻らずに高音へ進むこと、顎を開きすぎずに力まず発声すること、高音を後ろに引っ張らずに前へ飛ばす意識を持つこと、軽く笑顔を意識して口の形を整えること。「圧縮して飛ばす」ためには、息継ぎをしっかり行い、腹式呼吸で息に余力を持たせることが大切。母音ごとに共鳴するポイントが異なるため、意識的に口腔・鼻腔・咽頭の形を調整しながら、響きを維持・コントロールすることが必要になる。
少し話は逸れるが、ランニング30分後に歌うと声がよく出る。運動後は副交感神経が働き、余計な力みが抜ける。プールに入った後のように血行が良くなり、リラックスした状態になるので、響きやすくなる。確かに、身体が温まっていると声が伸びやすい感覚はある。これは今後のトレーニングにも活かせそうだ。
プロの歌声には、「楽に出ているように聴こえる」ことが不可欠。聴き心地のいい歌、気持ちいい声は、響きが豊かで、無理をしている感じがない。逆に、頑張りすぎると歌詞が伝わりにくくなる。J-POPのように歌詞をしっかり届けるジャンルでは、特に力まないことが大切。だからこそ、力を抜く技術こそが最も重要になる。
意識するべきなのは、表情筋をしっかり使い、ピッチが上がっても響きを一定に保つよう調整すること。高音になっても喉周りを力ませず、横隔膜や声帯筋を「ふんばる」感覚を持つこと。高音を出すときは響きの通り道を意識し、そこへ声を当てるイメージを持つこと。響きの余裕をしっかり確保することで、力みのない綺麗な高音が出せるようになる。
ライブでは、前半と後半で感覚が変わる。後半になると疲れて感覚が鈍ることもあるけれど、普段の練習で培った技術がそのまま出る。だからこそ、日頃から力を抜くことを意識するのが重要だ。
こんなふうに、歌は本当に楽しい。春の景色を眺めながら散歩し、こんなことを考えながら鼻歌を歌うだけで、何時間でも一人で楽しめる。
さて、今日は仕事の関係で受験する国家資格の二次試験対策をする。ロールプレイや口頭試問の練習を、職場の仲間たちと集まってやる予定だ。ポイントは頭の中で整理できているから、あとは実践で再現できるかを試したい。こういう「整理して、実行して、修正する」という流れは、音楽の制作やトレーニングと共通する部分が多い。やっていることの本質は同じだから、これもまた自分の得意なことのひとつだと感じる。
春は別れと新しい環境が交差する季節。家族や仲間も、それぞれの場所で新しいことにウキウキワクワクしながら、一生懸命生きている。それを感じるだけで、心が温かくなる。今日も離れていても、心は一つ。愛してるよ。それじゃあ、今日もありがとう。行ってきます!
お気に入り