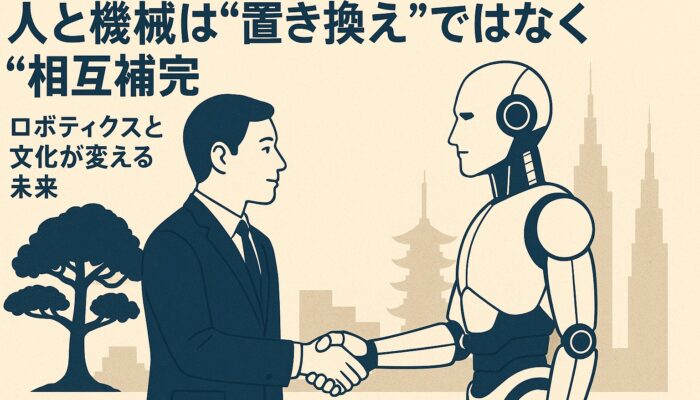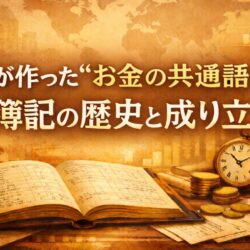おはよう。今日も広島は雨。でも、すっかり暖かくなった。
最近のボイストレーニングでは、ただ探っている段階を超え、真に求めていたものにたどり着き、それを洗練させるプロセスに入っている。僕が常に追求しているのは、声帯筋を活かした発声であり、これは裏声と同じ筋肉を使いながら、喉や顎に余計な力を入れず、楽に高音を響かせる方法だ。声帯を適切にコントロールし、声帯閉鎖を伴った「混じった声」を作る。これこそ、ポップスで言うところのミックスボイスにあたる。
ただ、ここで重要なのは、頭声、鼻腔共鳴、ミックスボイスの概念を正確に理解することだ。昔はこれらを混同し、思考の中で絡まり合っていた。しかし今は、それぞれがどう機能し、どう関わり合っているのか、明確に見えてきた。
頭声とは、頭で響かせる発声技術のことを指す。胸に響かせるためには、まず口腔内の空間を意識し、その響きを最大化する。その響きをさらにコントロールし、頭へと持ち上げることで、共鳴ポイントが引き上げられ、頭に響くようになる。これはミックスボイスや鼻腔共鳴とは異なる概念であり、ミックスボイスの中にも頭声の要素が入る。
鼻腔共鳴についても、間違った解釈をしている人が多い。よくある誤りは、鼻声になってしまい、口腔への息の量が減って鼻だけに音がこもることや、鼻から息漏れしてしまい、響きがなくなってしまうことだ。正しくは、口腔の響きを最大化することが最優先であり、舌の力を抜き、軟口蓋を適切な位置で保ち、鼻腔へと音の通り道を確保することが重要になる。ここで意識すべきなのは、鼻の穴から息を漏らさないことであり、鼻腔共鳴とは、鼻腔に響きを持たせるための技術であって、決して鼻声や息漏れを伴うものではない。
鼻腔共鳴は、単に「鼻に響かせる」ものではなく、口腔の響きを最大限に活かしながら、適度なバランスで鼻腔にも共鳴ポイントを作ることが重要になる。あくまで主軸は口腔の響きであり、それを損なわずに鼻腔にも適切に響きを与えることで、より豊かで自然な発声が可能になる。口の中の空間を確保し、舌や顎に余計な力を入れずに声を響かせることで、声の芯がしっかりと保たれたまま、鼻腔共鳴が生きてくる。これにより、声が軽やかに通り、無理なく高音へとつながっていく。このバランスが正しく取れていないと、鼻声になったり、逆に響きが不足した平坦な声になってしまう。
こうして整理すると、ミックスボイスは裏声と同じ筋肉(声帯筋)を使いながら、声帯閉鎖を加えて強さを持たせる発声であり、鼻腔共鳴は口腔の響きを最大化しながら鼻腔にも適度な共鳴ポイントを作る技術であり、頭声は声帯を薄く引き伸ばし、共鳴ポイントを頭へと引き上げる発声方法であることがわかる。つまり、ポップス的なミックスボイスとは、裏声と同じ発声機構を使いながら、地声の要素を取り入れた声と言えるし、声楽的な観点からは「裏声に制される声」とも表現できる。
この理解が深まると、無駄な力を入れる必要がなくなり、顎や舌の緊張が抜け、自然に声を出せるようになる。口を大きく開けすぎることもなく、むしろ親指を噛む程度の開口で十分であり、ガバッと開けすぎると舌や顎に力が入り、逆に響きを損なうことになるからだ。
僕は、毎日、特別に長時間ボイトレをしたわけではない。仕事をしながら、生活の中で、お風呂に入りながら、通勤しながら、鼻歌を歌っているうちに、点と点がつながっていく。まるで自然に降りてきたような感覚だった。「これまでの知識が統合された」と、毎日が楽しい。
今日は、来週の国家試験二次試験(口頭試問)のロールプレイング対策を、仲間たちと一緒にやる予定だ。楽しみだ。それぞれの場所で頑張っているみんなへ。卒業式や終業式を前にドキドキしている子供たち、みんな愛してる。体調を崩したり、風邪をひいた子供たち、早く元気になりますように。年度末の仕事や生活に追われている大人たち、みんな応援してる。遠く離れていても、心はひとつ。愛してる。バイバイ。
お気に入り